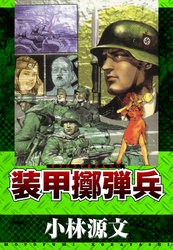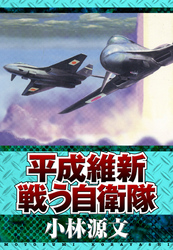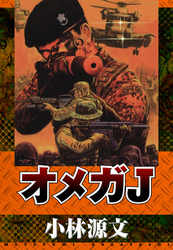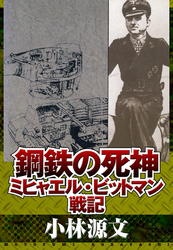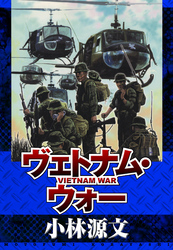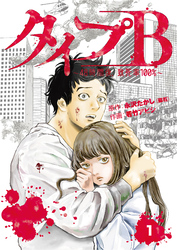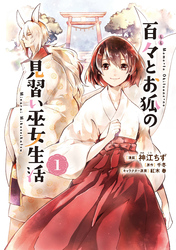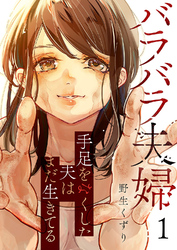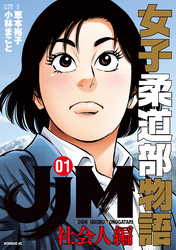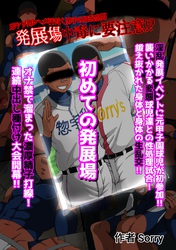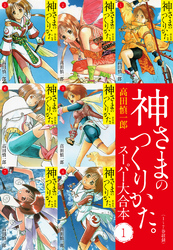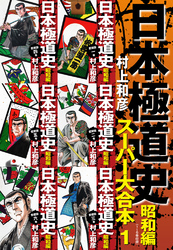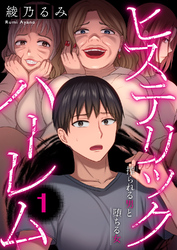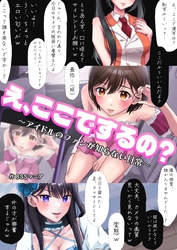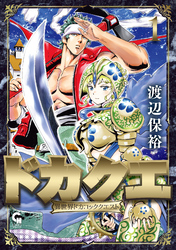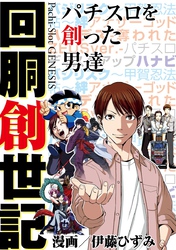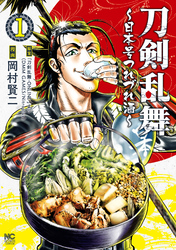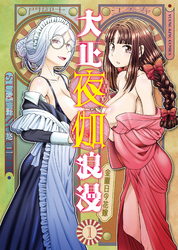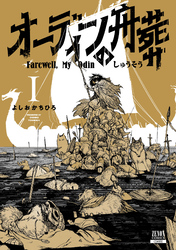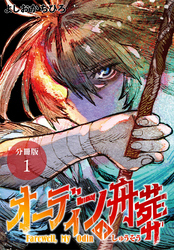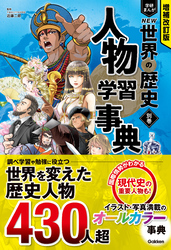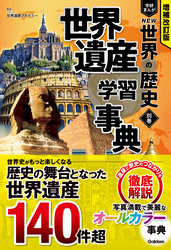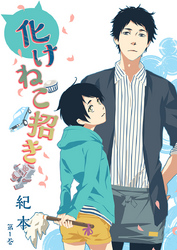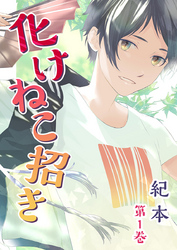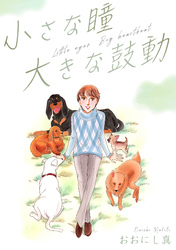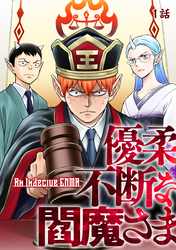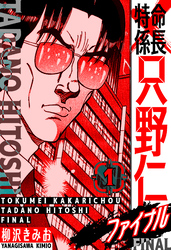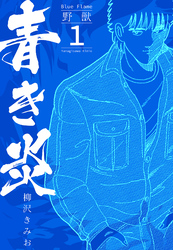山手線「駅名」の謎
あらすじ/作品情報
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。山手線の駅名に秘められた“東京の正体”を解き明かす!・「渋谷」の地名は“盗賊”と“伝説の武士”が関係していた?・「大塚」は『八犬伝』ゆかりの地。“塚”は古墳のこと?・「品川駅」実は鉄道創業の地! なぜ品川区にないの?・「有楽町」の名は、織田信長の弟・有楽斎に由来している?・「秋葉原」は火除けの神“秋葉権現”の名にちなんでいた!本書は、江戸文化歴史研究家・小林明が、日本で最も知名度の高い鉄道路線「山手線」全30駅の背後に眠る歴史・地名・土地の記憶を、丁寧に掘り起こした一冊です。各駅の由来を解き明かすことで、現代東京の“地形と地名の謎”がつながっていく。歴史好きはもちろん、地図好き・鉄道ファン・東京を歩くすべての人へ。※開業当初の駅舎や古地図なども多数収録※ビジュアルブックとしても楽しめます!■目次・はじめに・山手線の遍歴・東京・皇居の正面に立つレンガ造りの駅舎は貴重な文化遺産・神田・伊勢神宮の領田「神の田んぼ」に由来・秋葉原・「火除の神」秋葉権現が駅名の起源・御徒町・江戸時代の下級武士の役職が駅名となった珍しいケース・上野・江戸の鬼門封じ寛永寺のお膝元、山の手と下町の境に立つ巨大ターミナル・鶯谷・都から連れてきた鶯が美しいさえずりを響かせたという伝説の地・日暮里と西日暮里・風情あふれる「日暮らしの里」は「新堀(新しい堀)」が起源か?・田端・山の手と下町の境界に位置する「端」の駅・駒込・「駒」はヤマトタケルが目にした馬という伝承も・巣鴨・徳川慶喜は鉄道建設の騒音に耐えかねて逃げ出した・大塚・大塚の「塚」は古墳か、櫓か、一里塚か?・池袋・ホテルメトロポリタンあたりにあった農業用水の水源「丸池」が駅名の由来・高田馬場・駅名の由来となった弓馬の訓練場は江戸名所の1つだった・新大久保・新宿に近い多国籍タウンの最寄駅名は「窪んだ地」・新宿・「新しい宿場町」が駅名の由来となった乗客数1位の駅・代々木・「代々伝わる木」を起源とする地名が戦国時代からあった?・原宿・「宿場」を示す古くからの地名が地図から消え、駅名にだけ残った・渋谷・畑作地帯だった「渋谷村」、さらにさかのぼれば「塩谷の里」・恵比寿・「ビール」の商品名に由来する全国でも珍しい駅名・目白と目黒・ともに江戸を護るお不動さんにちなむ不思議なつながりを持つ駅・五反田・「五反」=70メートル四方の土地が駅名となった?・大崎・「多くの谷」が入り込むところから「谷→崎」に転じた説が有力・品川・新橋よりも先に仮開業した鉄道発祥の駅・高輪ゲートウェイ・賛否を呼んだカタカナ駅名は江戸時代に築かれた「門」・田町・「田」ばかりの農村が東海道の発展とともに「町」へ・浜松町・家康にゆかり深い「浜松」の地名を冠し徳川幕府の歴史が盛りだくさん・新橋・江戸時代初期に架けられた「新しい橋」はどこにあったのか・有楽町・駅名が織田信長の弟・有楽斎に由来する説は眉唾・おわりに・主要参考文献■著者 小林明(こばやしあきら)1964年、東京都生まれ。スイングジャーンル社、KKベストセラーズなど出版社の編集者を経て、2011 年に独立。現在は編集プロダクション、株式会社ディラナダチ代表として『歴史人』(ABC アーク)、『歴史道』(朝日新聞出版)などの編集を担当するほか、日本情報多言語発信サイト「nippon.com」、「和樂web」(小学館)、交通・運輸・モビリティ産業ニュース「Merkmal」、「ダイヤモンド・オンライン」(ダイヤモンド社)、法律サイト「弁護士JPユース」などに歴史・文化風俗史の記事を執筆中